🎨 スカーフで楽しくリズム遊び&いないいないばあ!
ふんわりスカーフを使って、リズムを体で感じる遊びがいっぱい!「いないいないばあ!」で笑顔になりながら、拍子を聞き分ける力が身につきます。
🌸 季節感たっぷりのピクチャーカードで表現力を伸ばそう!
冬季節のピクチャーカードを使って、楽しく表現力を高めます。お子さまの感性を育てながら、英語の単語もどんどん覚えられます!
リトミックは、心を育てる最高の方法
子どもたちとご家族さまに求められている、 すばらしい教育法
子どもは、あそぶことが大好き!遊びのなかで、感じたり、考えたり、喜んだり、悲しんだり、驚いた りしながら成長していきます。そんな子どもたちの成長に大切なのは、「知ること」より、「感じるこ と」であると思います。リトミックは、その感じる心を育てる最高の方法です。音楽を感じ、動くこと により、感じる心、想像力や創造力を養います。また、心で感じたものを、からだを使って自由に表 現することで、心と体の協調と調和を作りだそうとします。
子どもたちは、楽しい音楽を聴くと、か らだいっぱいでウキウキワクワクを表現して、静かな音楽を聴くと静かに歩くなど、こどもたちが感じ て表現する能力にはいつも感動しています。
自由に走り回っていた子どもが、音楽に合わせて集中して表現をする姿をみると、その集中力に驚か されます。恥ずかしがりやの子どもたちが、少しずつ表現できるようになっていく姿に、自立心や表 現力の成長を感じます。そして、お友達と一緒にひとつのことを表現する姿に、社会性や共同性の育 ちを感じます。
こどもたちの成長は目覚ましく、リズム感や音 はぐんぐん育ち、楽しそうに合奏をしたり、いき いきと体いっぱいで表現する姿に、ご両親も限 動してくださる場面もたくさんあります。
幼稚園教育要領でも、保育所保育指針でも、「 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として、 ・自立心・共同性・豊かな感性と表現を目標に することとあります。まさに、リトミックは、幼児 「期の終わりまでに育ってほしい姿に近づける 高の教育法です。
①「楽しさ」だけじゃない!IICOkidsリトミックレッスンで子どもたちの成長を実感しませんか?
「リトミックって、ただ音楽に合わせて踊ったり歌ったりする遊びでしょ?」と思っている方もいるかもしれません。でも、IICOkidsのリトミックレッスンはそれ以上です!
IICOkidsでは、リトミックの国際資格を持つ講師が、実際のレッスンを通して作り上げた特別なプログラムを提供。子どもたち が楽しいだけでなく、一つ一つの内容に音楽的な意味が含まれていて、子どもたちの成長をハッキリ実感できる プログラムです。
本当に良い教育プログラムだからこそ、子どもたちは「できた!」という達成感を味わい、自分の成長を楽しみながらレッスンを続けることができます。
そして、その成長の喜びは、子どもたちだけでなく、保護者の皆さまにも感じていただけます。
②認定専門講師による、質の高いリトミックレッスン
IICOkidsのリトミックレッスンは、レッスン内容や使用教材があらかじめ決められており、安定した質とレベルを確保しています。
レッスンを担当する先生は、リトミックの基礎をしっかり学び、ピアノの即興演奏で子どもたちを楽しく、効果的に指導できるスキルを持っています。
リトミックとは
私たち人間は、感情のコミュニケーションの手段として 言語だけでなく、音楽という手段を持っています。
「音楽を聴いたり、演奏する事によって、知性にかなり影響が出る」ということ 多くの科学者が唱えています
では、なぜ音楽を聴いたり演奏することが知性に影響するのでしょうか?
それは、聴覚システムが右脳を使ってパターンを推測し、それを発見します。例えば、音楽の始まりや終わりの感覚、拍子やリズム、調性感など音楽に含まれる色々な要素を素早く頭の中で分析し、理解しようとするからです
音楽的能力には、大きく2つの段階が考えられると思います
1. 聴いたことに対する知覚能力
音やリズム、音質など、外部から与えられる音楽的要素を認識し、それに反応する能力。
2.音楽を表現する能力
自分の身体の中から働くもの、音やリズムの知覚、そして表現の方法も、音楽的な発達レベルにより どんどん変化し、育っていきます。
こどもは1人1人まったく違う成長をします。そんな個性豊なこどもたちに、大人が無理に物事を押しつけるのではなく、こどもの発達を認識し、発達に合わせた音楽遊びを展開することで、こどもの持っているものを、こどもの中から引き出して より豊かな音楽性を身に付けて欲しいと思っています。



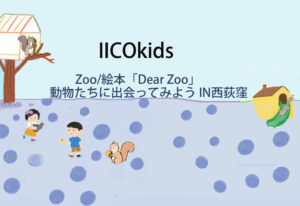



コメント